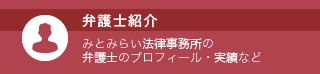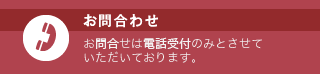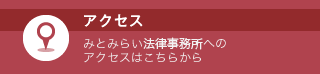普通解雇は簡単にはできません
普通解雇
1,前回の復習
懲戒処分は、業務命令や服務規律に違反するなどして企業秩序を乱した労働者に対して、使用者が制裁として行う罰です。懲戒処分には、戒告、譴責、減給処分、出勤停止、降格、諭旨退職、懲戒解雇などがあります。懲戒処分を検討しなければならないような事態に至ったときには、ついカッとなり、冷静さを失い、やり過ぎてしまうおそれがあります。ですので、落ち着いて、より慎重に対応するように心がけていただきたいとお話しをさせていただきました。懲戒処分のうちもっとも重い処分は懲戒解雇です。今回は、懲戒解雇に似ている普通解雇についてお話ししたいと思います。
2,労働契約の終了原因
労働契約が終了する原因には,いくつかあります。
A 当事者である労使の合意による労働契約の解約
B 労働者からの辞職
C 使用者からの解雇
D 労働期間満了
E 定年
F 休職期間満了時の当然退職
等があります。
このうち解雇とは,労働契約を終了させる使用者の一方的な意思表示です。
解雇には,普通解雇と懲戒解雇があります。
懲戒解雇は,労働者に非違行為があるときに,懲戒処分として労働契約を終了させることをいいます。
普通解雇は,懲戒処分ではありませんので、労働者に非違行為があるか否かを問いません。
普通解雇には、能力不足,勤務態度不良,業務命令違反等,労働者に責任のある事由による解雇などがあります。
3,普通解雇への制約
使用者は労働者を自由に解雇できるのでしょうか。
ときどき相談を受けると、1ヶ月分の給与を支払いさえすれば解雇できると簡単におっしゃる経営者の方がおられますが、ご存じのとおり、そのようなことはありません。
普通解雇には、いろいろな制約があります。
普通解雇が有効となるかを判断するためには,以下の点を検討しておく必要があります。
① 就業規則の普通解雇事由に該当するか
② 解雇権濫用(労契法16条)に当たらないか
③ 解雇予告義務(労基法20条)を遵守しているか
④ 解雇が法律上制限されている場合に該当しないか
これらの点について、順に見ていきましょう。
4,就業規則と普通解雇事由
就業規則に解雇事由として具体的に定めてあれば問題はないのですが、もし就業規則に具体的に定められていないことをした場合に、それを理由に普通解雇できるでしょうか。
具体的に考えてみましょう。
たとえば,就業規則に
(解雇事由)
第23条 従業員は、次の各項の事由に該当する場合は解雇する。
(1)身体または精神の障害により、業務に耐えられないと認められたとき
(2)勤務成績が不良で、就業に不適格であると認められたとき
とだけ記載されていたとします。
この会社内において、ある従業員が,会社の許可を受けず職場で過激なアジ演説した場合に,この従業員を解雇できるのでしょうか。
上記の解雇事由には、アジ演説をした場合に解雇事由にあたるとの記載はありません。
就業規則上の解雇事由の定めが解雇事由を限定的に列挙したものか(限定列挙説は書かれていること以外は認めません)、あるいは例示的に列挙したものか(例示列挙説は、単なる例として記載されていると考えるので、記載されていなくとも認めます)の争いがあります。
限定列挙説に立つと、使用者は就業規則上の解雇事由のいずれにも該当しないのであれば普通解雇はできないという結論となります。
裁判例はどうなっているのでしょうか。
裁判例の多くは、就業規則に書かれていること以外は認めない限定列挙説の立場に立っているようです。そうであるとすると、普通解雇事由として記載されていないと解雇はできないことになります。
そのようなことにならないようにするために,就業規則の普通解雇事由として最後に「その他,前各号に準じる事由があるとき。」といった包括的な条項を入れておきましょう。
5,解雇権濫用(労契法16条)に該当しないか
労契法16条は,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」と定めています。解雇権の濫用は無効となります。
仮に,ある解雇が無効となると,どうなるかといえば,解雇したはずの社員は解雇されていないことになります。法律上は雇用関係が続いており、在職中の扱いとなります。
そうすると,実際には働いていないにもかかわらず,解雇後の期間について使用者は賃金を支払わなければならないことになります。
- 「普通解雇に客観的に合理的な理由」があるとは
経営者がこの労働者には解雇する必要があると主観的に判断しただけでは不十分で客観的に合理的な理由がなければなりません。
ここで、ちょっと、脱線します。
法律家の文章に、「主観的」「客観的」という言葉が使われることが多いのですが、わかったようで実はわからない気分になります。そこで、意味を調べてみましょう。
「主観的」とは、自分1人だけのものの見方や、感じ方にとらわれていることを指します。「主観的」の反対語は「客観的」で、これは第三者の立場からものごとを観察し、考えられることです。
また、「合理的」という言葉もよく使われます。これは、物事を筋道立てて考えて、理屈や道理に合っていることをいいます。
「客観的」に「合理的」な理由があるとは、第三者の立場から見ても、理屈や道理に合っているという意味になります。
「普通解雇に客観的に合理的な理由」というのは、それが第三者の立場から見ても、理屈や道理に合っている、すなわち、労働契約を終了させなければならないほどに程度が甚だしく,業務の遂行や企業秩序の維持に重大な支障が生じているということです。
②「普通解雇が社会通念上相当」とは
こちらも言葉の意味を調べてみましょう。
「社会通念」とは、デジタル大辞泉によると社会一般に通用している常識または見解のことです。また、「相当」とは、大辞林(第三版)によると、「状態・程度などが釣り合っていること。ふさわしいこと。相応。違った尺度や体系上のあるものと等しいこと。対応すること。物事の程度や状態が釣り合っているさま。ふさわしいさま。」とあります。つまり、「社会通念上相当」とは社会一般の常識からみて、釣り合っているという意味になります。これを解雇の文脈で使うと、社会通念上相当であるかは,社会常識から見て、その労働者がやったことと解雇が釣りあっていてふさわしいということです。
このふさわしいかどうかを判断するのに、さらに細かく分けていくと、
労働者の情状(反省の態度,過去の勤務態度・処分歴,年齢・家族構成等)
他の労働者の処分との均衡
使用者側の対応・落ち度等
に照らして,解雇がふさわしい、解雇がやむを得ないと評価できることが必要です。
解雇権濫用の有無を判断する具体的な事情としては,以下のようなものあげられます。
① 当該企業の種類,規模
② 職務内容,労働者の採用理由(職務に要求される能力,勤務態度がどの程度か)
③ 勤務成績,勤務態度の不良の程度(企業の業務遂行に支障を生じ,解雇しなければならないほどに高いかどうか)
④ その回数(1回の過誤か,繰り返すものか),改善の余地があるか
⑤ 会社の指導があったか(注意・警告をしたり,反省の機会を与えたりしたか)
⑥ 他の労働者との取扱いに不均衡はないか
などを総合検討することになる(労働事件審理ノート第3版P26参照)
6 解雇予告義務(労基法20条)を遵守しているか
使用者は,労働者を解雇しようとする場合においては,原則として,少なくとも30日前に解雇予告するか,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法20条)。言い換えると、解雇の30日前に予告すれば解雇予告手当を支払う必要はありませんし,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば,即時解雇することができます。
7.解雇が法律上制限されている場合に該当しないか
労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇,女性労働者の妊娠,出産,産前産後休業等を理由とする解雇,労働基準法違反の申告を監督機関にしたことを理由とする解雇,性別を理由とする解雇,不当労働行為の不利益取扱いとなる解雇,公益通報をしたことを理由とする解雇等の一定の場合については,法律上解雇が制限されています。したがって、これらに違反する解雇は無効となります。
8,退職前の社員に関する注意点
解雇予告されると,その社員の働くモチベーションは下がります。そのため、ミスを犯しがちです。解雇予告をした場合は、最後まで社員が業務上のミスをしないように注意を払いましょう。
また、考えたくないことですが、解雇予告された社員の中には,自分を解雇した会社のことを恨んで腹いせをしようと考える者がわずかながらいることも事実です。
そのため、会社の機密情報を不正に持ち出したり,消去したり可能性も否定できません。これらを防止するために,解雇予告後は,会社のパソコンは使わせず,機密情報にはアクセスさせないようにすることも必要かもしれません。
その他の記事ARCHIVE
- 2023.09.02 後藤 直樹
- なかなか相続対策が進まない親の心理…
- 2023.08.02 後藤 直樹
- 争族にしたくないなら対策しましょう…
- 2023.08.01 後藤 直樹
- 事務所移転のお知らせ…
- 2023.07.28 後藤 直樹
- 従業員のソーシャルメディア利用について…
- 2023.07.26 後藤 直樹
- ヘルメット着用義務化について…